めざせ!夢の立身出世
慶応3年(1867年)、正岡子規(まさおかしき)は愛媛県松山市に生まれました。本名は正岡常規(まさおかつねのり)で、城下町の武家の長男でした。
 正岡子規
正岡子規
16歳の常規の夢は1日も早く東京に行き、立身出世を果たすことでした。
我々は社会の上流に立つことを願う者であるから学問勉強を手段にして必ずその域に至らねばならない。
(明治16年2月13日付 叔父への手紙より)
明治16年(1883年)念願の上京を果たした常規は、東京大学予備門に入学しました。ところが、授業はちんぷんかんぷん。数学の授業でさえ英語で行われるのに、常規は英語が大の苦手だったのです。さらに、ある試験では前日に友人と酒を飲んでしまい散々な結果に。
試験には満点百のものをようよう十四点だけもらった。十四点とは余り例のない事だ。酒も悪いが先生もひどいや。
(ホトトギス第二巻第九号より)
落ち込むどころか居直って人のせいにするふてぶてしさ。それでも立身出世は諦めず、目指すは哲学の博士。当時、西洋から入ってきたばかりで最先端のかっこよさげな学問でした。
ところが、常規はこれも早々に断念。原因はクラスメイトの米山保三郎でした。米山は常規と同じコース116人のうち5人の特待生に選ばれるほどの秀才でした。米山が読む哲学書は常規が読んだことのないものばかり。知識も比べものになりませんでした。圧倒された常規はわざわざ友人にこう宣言しました。
常規はすぐに次の道を見出しました。文学です。明治20年代、人気の小説家が次々と登場。小説が隆盛を極めていました。これからの時代は文学だと小説家を目指し部屋にこもって執筆にとりかかりました。
明治25年(1892年)、自分が持つあらゆる文学の知識を結集させた渾身の小説「月の都」が完成。男女の悲恋物語です。常規は意気揚々とプロ作家のもとに「月の都」を持ち込みました。相手は新進気鋭の作家・幸田露伴(こうだろはん)でした。露伴僕の小説を評して曰く「覇気強し」と。つまり力の入り過ぎということ。これにはさすがの常規もがっかりでした。
なぜ?くじけぬ強さの秘密
しかし常規はあっさりと立ち直り、2ヶ月後には後輩に新たな目標を宣言しました。
僕ハ小説家とナルヲ欲セズ詩人トナランコトヲ欲ス。人間よりハ花鳥風月がすき也。
(友人への手紙より)
こうして詩の世界に身を置くこととなったのです。夢が次々と破れても哲学者、小説家、詩人と新たな目標を見出す常規。そこには苦難を乗り越えるための知恵がありました。
知恵その一
「いろんな自分」をつくり出そう!
常規は多くの俳号・ペンネームを持つ名前マニアでした。10歳の頃から文章を書くたびにペンネームを使い、その数は100以上。
例えば、面白おかしいおどけた文章を書いた時には「落語生」、流麗な短歌の時には「竹ノ里人」と。多くの名前を持つことで様々な状況、人格を楽しんだのです。このことが、常規を襲う最悪の事態をも乗り越えていく知恵となりました。
明治22年(1889年)、常規は喀血。原因は肺結核でした。自分の命は長くないことを悟った常規はその思いを一句。
卯の花の散るまで鳴くか子規(ホトトギス)
口の中が赤いホトトギス。吐血する肺結核患者は、その様子から当時ホトトギスに例えられていました。これ以降、常規はあえて自らを結核を表す子規と名乗るようになりました。
正岡子規は絶望の中にある自分にも新たな名前をつけることで、苦しみを楽しみに変えていったのです。
強引にもほどがある!?
正岡子規は好きなことには何でも強引に友人を巻き込みました。当時、アメリカから入ってきたばかりの野球にも大勢の仲間を誘いました。特にしつこく連れまわしたのが生涯の親友・夏目漱石です。
 夏目漱石
夏目漱石
漱石は正岡子規をこう回想しています。
何でも大将にならなけりゃ承知しない男であった。二人で道を歩いていてもきっと自分の思う通りに僕をひっぱり廻したものだ。
(夏目漱石の回想)
余ハ偏屈なり 頑固なり すきな人ハ無暗にすきにて嫌ひな人ハ無暗にきらひなり
「筆まか勢」より
なぜ?友に慕われる秘密
明治28年(1895年)、正岡子規は肺結核の療養のため松山に帰省しました。同じ時、英語教師として松山にいた夏目漱石は結核がうつることも恐れず、正岡子規を自分の下宿に住まわせました。
正岡子規が漱石の下宿で過ごした2ヶ月は、毎日のように友人が訪れ句会が開かれました。強引で無遠慮にもかかわらず、正岡子規が友人たちに慕われるのにはこんな知恵がありました。
知恵その二
友の人生にとことん関われ
正岡子規は友人と一度関わると最後まで関わり抜きました。東京で共に学んだ友人・清水則遠(しみずのりとお)が病で亡くなった時、故郷の兄弟に送ったお悔やみの手紙が残っています。
その長さは何と8メートル。そこには死をみとった正岡子規が仲間にカンパをつのり葬儀を行ったこと、清水が亡くなった時の状況から墓標には何と刻んだか、棺の形に至るまで詳細に報告。そして友として清水を救えなかったことの謝罪と無念の思いを繰り返しつづったのです。長い手紙にはこんな一節も。
ご令弟の名をあげることを今後の自分の一生の目的にするつもりです。そのためにはまず第一に僕の名をあげることに務め命を懸けようと思います。
正岡子規のありあまる友情について、何度もおせっかいを受けた友人はこう記しています。
時として小五月蠅く感ぜしめたこともあったが、友を思ふこと厚く、誠心誠意であり、エラがらうとするのでは無いのであった。
(友人 寒川鼠骨の回想)
俳句仲間に囲まれた晩年。友人たちは当番を決め、病に苦しむ正岡子規を毎日のように見舞いました。病床の孤独は友人たちによって癒されたのです。
余は交際を好む者なり 何故に好むや 良友を得て心事を談じ 艱難相助けんと欲すれば也 兎に角 交際を始めたらば 熱心に交際する方也
「筆まか勢」より
知恵その三
ささやかなことに輝きを見いだせ
正岡子規は20代の終わり頃、昔からのルールに縛られていた俳句の世界に革新を起こしました。目の前にあるものを見て感じたことを思うままに句にする「写生」が大切だと提唱したのです。
正岡子規は松山で療養中にも市内を散策し写生の句を多く詠もうと試みています。正岡子規は沢山の風景に触れ、それを写し取るように句をつくることに力を注ぎました。そして、松山から東京に向へかう道中、立ち寄った奈良で名句が誕生しました。
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
やがて、外の世界をみにいくことが叶わなくなっていきました。明治29年(1898年)、正岡子規は28歳の時に肺結核が脊椎カリエスに進行。背中や腰に穴が開き膿があふれ激痛に絶叫する毎日でした。
ほーたい取替のとき ちょつと見るに 真黒になりて腐り居るやうなり 定めてまた穴のあくことならんと思はる このこと気にかかりながら午飯を食ひしに 飯もいつもの如くうまからず 食いながら時々涙ぐむ
「仰臥漫録」より
病床六尺 これが我世界である しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである
「病牀六尺」より
外との繋がりを感じられるのは、庭の草花を眺める時だけになりました。目の前の命をより精細に描き出すことに正岡子規は没頭しました。一番の楽しみは水彩画を描くことでした。
草花の一枝を枕元に置いてそれを正直に写生して居ると造化の秘密が段々分つて来るやうな気がする。或る絵具と或る絵具とを合せて草花を画く。それでもまだ思ふやうな色が出ないと、また他の絵具をなすつてみる。神様が草花を染める時もやはりこんなに工夫して楽しんで居るのであらうか。
「病牀六尺」より
ささやかな草花を前に宇宙の秘密にまで思いをめぐらせ、限られた世界の中で正岡子規の心は自由でした。
山吹と見ゆるガラスの曇哉
物思フ窓ニブラリト絲瓜哉
身動きがほとんどとれなくなってからも友人たちは何度も正岡子規のもとに集い、句会が行われました。友人が帰り際「お大事に」と言うと、正岡子規は「ナニその中に死んでしまいます」と答えたと言います。
そして明治35年(1902年)9月19日、正岡子規は34年の生涯を閉じました。最後の春のある日、こう記しています。
ガラス玉に金魚を十ばかり入れて机の上に置いてある
余は痛をこらへながら病床からつくづくと見て居る
痛い事も痛いが綺麗な事も綺麗ぢや
「先人たちの底力 知恵泉」
正岡子規 心がラクになる五・七・五
~苦難を楽しんだ青春~

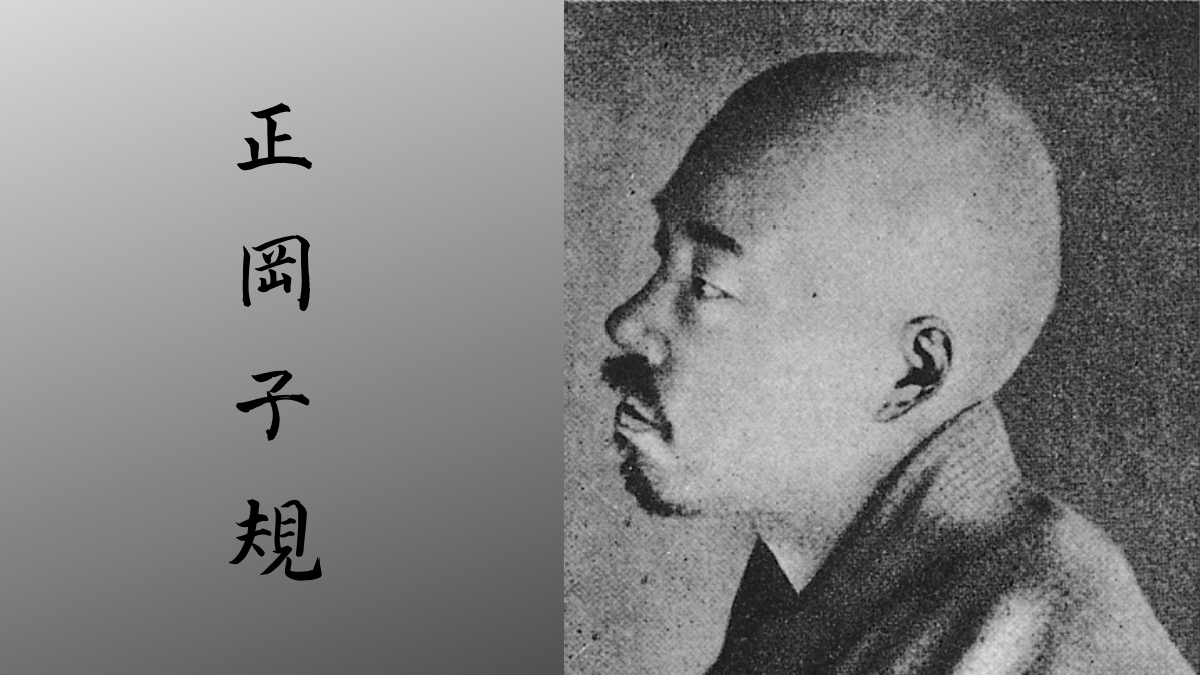
この記事のコメント